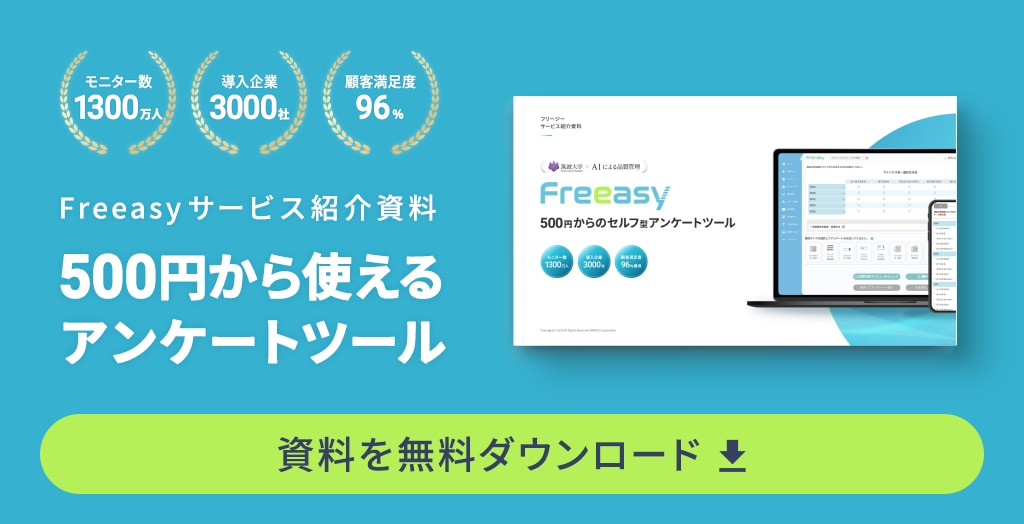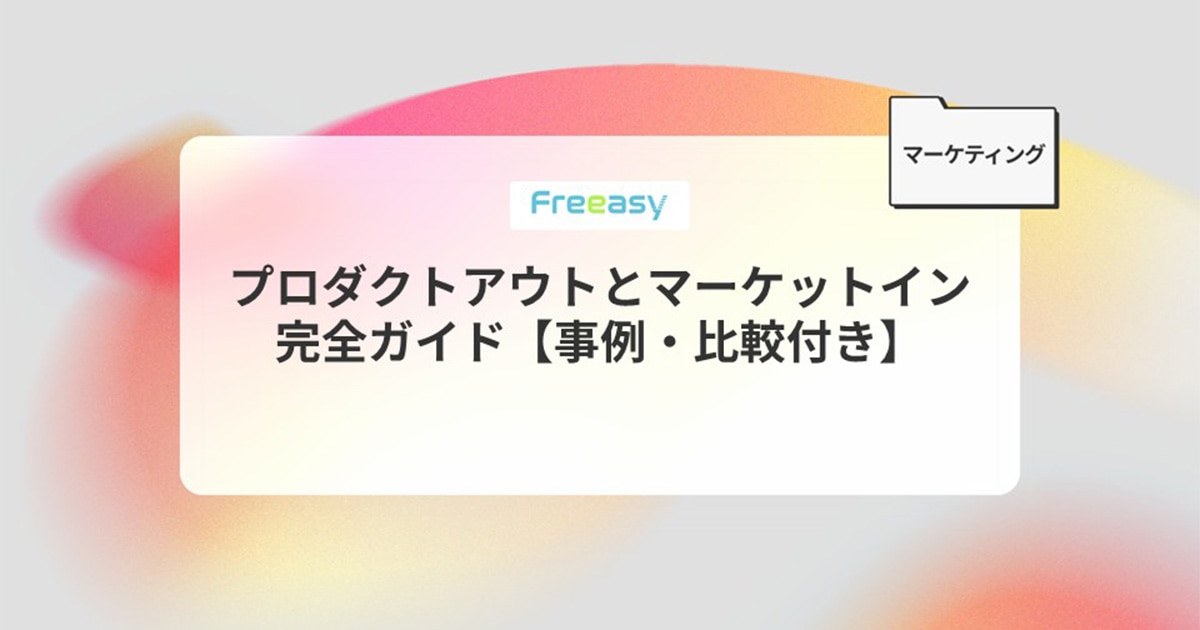
プロダクトアウトとマーケットイン完全ガイド【事例・比較付き】
📥無料ダウンロード【お役立ち資料】プロダクトアウトとマーケットイン ハンドブック
目次[非表示]
- ・はじめに
- ・プロダクトアウトとマーケットインの比較表
- ・プロダクトアウトとは
- ・プロダクトアウトの成功事例
- ・マーケットインとは
- ・マーケットインの成功事例
- ・発想の使い分け方~プロダクトライフサイクルに合わせた選び方をする~
- ・プロダクトアウトとマーケットインの歴史
- ・プロダクトアウトとマーケットインの融合、今後の展望
- ・まとめ(プロダクトアウトとマーケットインの比較)
- ・プロダクトアウトとマーケットインにまつわる、よくある質問
- ・Q:プロダクトアウトとマーケットインのどちらが主流になるのかは、景気のように循環するのでしょうか。
- ・Q:プロダクトアウトとマーケットインの違いは、企業の体質に左右されるものなのでしょうか。
- ・ Q:メーカーや流通企業が消費者と一緒に商品やサービスをつくる『共創』も、マーケットインの考え方にあてはまるのでしょうか。
- ・ Q:社内で「プロダクトアウト」と「マーケットイン」のどっちを重視するか、部署ごとに対立することはありますか。
- ・ Q:プロダクトアウトとマーケットインの融合において、最も重要なポイントを教えてください。
- ・無料ダウンロード『プロダクトアウトとマーケットイン ハンドブック』
- ・おわりに
はじめに
ここではプロダクトアウトとマーケットインに関する基本的な説明と、事例を紹介していきます。
この記事を読んで分かること、できるようになること
- プロダクトアウトとマーケットインの発想の違いを正しく理解し、マーケティングへの活かし方が分かる。
- プロダクトアウトとマーケットインの歴史と現状を理解し、今後の展望を知ることができる。
- まとめた資料を、無料でダウンロードできる。
プロダクトアウトとマーケットインの比較表
まず最初に、プロダクトアウトとマーケットインの内容を簡潔に比較表にしました。
起点の違いをはじめとして多くの相違点があることが分かります。
こちらの表を踏まえたうえで、次から順に詳しく解説していきます。
プロダクトアウト | マーケットイン | |
起点 | 自社(作り手)のシーズ | ユーザー(買い手)のニーズ |
姿勢 | 良い商品・サービスを作れば売れる | 求められる商品・サービスを作れば売れる |
ニーズ | 顧客が気づいていない潜在ニーズ
| 顧客が「これが欲しい」という顕在ニーズ
|
主なメリット | ●自社独自の技術・アイデア・製造設備などの強みを活用できる ●開発コストを抑えられる ●革新的商品やサービスを生み出す可能性がある ⇒ブルーオーシャン創出 | ●ユーザーニーズを満たした商品やサービスが提供できる ●商品やサービスを効率的に作ることができる ●需要予測が立てやすく、事業計画とマーケティング予算が組みやすい |
主なデメリット | ●商品・サービスが売れない可能性が高い⇒その場合、改善や戦略の見直しが必要 ●それまでに存在しなかった商品・サービスの場合、売上が予測できない | ●「驚き」を与える革新的な商品・サービスは生まれない ●競合他社に模倣されることが多い⇒市場のレッドオーシャン化 |
影響 | 生活スタイルが変革されることもある | 生活が便利になる(生活のマイナーチェンジ) |
時代背景 | 大量生産・大量消費の経済成長期 | 商品・サービスが普及した成熟期 |
プロダクトアウトとは
プロダクトアウトとは、商品やサービスを開発するとき、自社のシーズ=自社が得意とする技術やアイデア、製造設備を起点とする発想のことです。※シーズには「種」という意味があります。
特徴(メリットとデメリット)
開発コストを大幅に抑えられる!
最大のメリットは、自社独自の技術・アイデア・製造設備などの強みを活用できるため、開発コストを大幅に抑えられることです。
革新的な商品・サービスを生み出す可能性がある!
いままでにない画期的で素晴らしい商品やサービスを生み出す可能性があることもメリットです。さらには新たな商品カテゴリーの登場により、生活者のライフスタイルが変革されることもあります。近年の事例としては、スマートフォン(iPhone)の登場が典型的です。
商品やサービスが消費者に受け入れられない可能性が高くなる!
メリットがある一方、最大のデメリットは、プロダクトアウトの起点は自社の立場であるため、商品・サービスが消費者に受け入れられない可能性が高くなります。
売り上げの予測が難しい
特に今まで世の中に存在しなかった商品やサービスの場合、売上の予測は困難となり、さらに売れなかった場合の要因分析にコストと時間がかかることにもなります。
プロダクトアウトの成功事例
1.ソニーのステレオカセットプレーヤー「ウォークマン」の成功事例
1979年、ソニーから音楽を聴くスタイルに革命を起こしたステレオカセットプレーヤー「ウォークマン」の1号機が発売されました。
開発当時、ソニー社内外では「録音機能なしでは売れない」という声が多数派でしたが、その常識に反し、「ウォークマン」は大ヒット、音楽享受の新たなライフスタイルを創造しました。
それまで家庭の高価なステレオセットに、アナログレコードをかけて聴いていた音楽が、カセットテープで場所を選ばず聴けるようになったこと(音楽のパーソナル化)で、発売される楽曲は若者向けに細分化されていきました。
ソニー創業者の井深氏は、「海外出張の飛行機内でステレオ音楽を聴きたい」と思いつき、モノラルテープレコーダーをステレオに改造しました。その改造機を試したもう一人の創業者の盛田氏は、「これはおもしろい!一日中音楽を楽しんでいたい若者の願いを満たすものだ」と独特のビジネス勘を発揮、迅速な商品化を指示、再生機能だけで開発していくことを決断しました。
同じ頃、超軽量ヘッドホンが開発されていたことも幸いし、そのヘッドホンとの組み合わせによって1979年、手のひらサイズのヘッドホンステレオプレーヤー「ウォークマン」が完成しました。
工夫を凝らした宣伝活動を行った同社は、いつでもどこでもステレオサウンドが楽しめるという新しいライフスタイルをアピールしました。
この新たな音楽の楽しみ方はあっという間に若者の心を捉え、「ウォークマン」はヘッドホンステレオ市場という新たなマーケットを作り出しました。
2.アップル「iPhone」の成功事例
2007年1月、アップルは革新的な携帯電話、タッチコントロールの付いたワイドスクリーンiPod、そしてデスクトップパソコン並のメール、ウェブブラウズ、検索、マップ機能を持つ画期的なインターネット通信デバイスという3つの製品を、1つの小型軽量ハンドヘルドデバイスに一体化した「iPhone(アイフォン)」を発表しました。
開発者の故 スティーブ・ジョブズ氏の、
「消費者に、何が欲しいかを聞いてそれを与えるだけではいけない。製品をデザインするのはとても難しい。多くの場合、人は形にして見せて貰うまで自分は何が欲しいのかわからないものだ」
というコメントは、多くのマーケターの関心を集めました。
「iPhone(アイフォン)」が日本で発売されたのは翌2008年の5月。タッチスクリーンで操作する機能は、携帯電話のボタン操作が当たり前と思っていた人々に、驚きと革命をもたらしました。
シンプルなデザインや美しいフォルム、そして直感的に操作できるiPhoneは、日本国内でもかなりのシェアを占めました。そしてiPhoneのモデルチェンジのたびに、「アップルストア」には行列ができるという社会現象まで生まれました。
マーケットインとは
マーケットインとは、商品やサービスを開発するとき、ユーザーのニーズを起点とする発想のことです。自社のシーズを起点としたプロダクトアウトとは正反対の発想になります。
特徴(メリットとデメリット)
ユーザーニーズを満たす商品やサービスを提供できる!
ユーザーのニーズを起点とするため、ユーザーニーズを満たした商品やサービスを提供でき、商品やサービスを効率的に作ることができます。
事業計画がたてやすくなる!
前述の通り、ユーザーニーズに応えた商品やサービスのため、需要予測が容易になり、マーケティング予算が組みやすい=事業計画が立てやすくなります。
LTV(顧客生涯価値)の上昇が期待できる!
マーケットインによって開発された商品の場合、独創性が全面に押し出されたものではなく、ユーザーの求める機能・性能を満たしたものになりやすい点が特徴です。
ゆえにリピート率の向上やロイヤリティの醸成により、継続利用によるLTV(Life Time Value/顧客生涯価値)の上昇が期待できます。
革新的な商品・サービスは生まれない
デメリットとしては、「驚き」を与える革新的な商品・サービスは生まれないことです。また、たとえ商品やサービスがヒットしたとしても、容易に競合他社に模倣されます(市場の“レッドオーシャン化”)。
ブランドイメージが迷走化するリスクがある
発想の起点がユーザーニーズやマーケットの動向であるため、開発された商品やサービスが、自社のイメージと大きく隔たってしまうリスクがあります(ブランドイメージの迷走化)。
マーケットインの成功事例
1.オタフクソース「お好みソース」の成功事例
広島県広島市に本社のあるオタフクソースは、1922年(大正11年)創業の老舗調味料メーカーです。戦前は醸造酢「お多福酢」を製造していましたが、戦後の1949年(昭和24年)、「洋食の時代」の到来を予見した同社はウスターソースの製造に着手、1950年(昭和25年)に「お多福ウスターソース」の製造・販売を開始しました。
ところが、当時のソース業界において同社は後発メーカーだったこともあり、「お多福ウスターソース」の販売は苦戦しました。
そこで同社は、直接「お多福ウスターソース」への意見を聞こうと、広島の屋台や飲食店の訪問を始めました。その中で出会ったのが、お好み焼き店でした。
お好み焼き店を一軒一軒訪問していくうちに、「サラサラとしたウスターソースは鉄板に流れ落ちる」という悩みを聴き、お好み焼きに合うようなソース造りでの試行錯誤を重ね、1952年(昭和27年)に「お好みソース」が誕生しました。
2.アサヒ飲料「WONDA モーニングショット」
1997年(平成9年)、アサヒ飲料の缶コーヒー「WONDA(ワンダ)」が発売されました。
当時の市場は有力メーカーの商品がしのぎを削る“レッドオーシャン”でした。メインチャネルのコンビニでは、「ジョージア」(日本コカ・コーラ)、「Roots」(JT)、「ファイア」(キリンビバレッジ)、「BOSS」(サントリー)、「UCC」(UCC上島珈琲)など、さまざまなブランドが日々棚のスペースを取り合っていました。
そして2002年、「WONDA モーニングショット」が発売されました。
当時、コーヒーの商品開発で用いられていたマトリクスは、「男性・女性」×「年齢高い・低い」という顧客軸マトリクスと、「ミルク・ブラック」×「加糖・無糖」という味軸マトリクスでしたが、アサヒ飲料のマーケティング担当者は、「朝・夜」×「年齢高い・低い」という「飲用シーン×男性特化」マトリクスを使いました。
それまでの市場調査で「朝に缶コーヒーを飲む男性が多い」という結果が出ていたことから、「思い切って【朝】と【サラリーマン】に特化した商品開発をしてみよう」と考えた結果でした。
「朝専用」というポジションは年代を超えた“ブルーオーシャン”だったのです。

発想の使い分け方~プロダクトライフサイクルに合わせた選び方をする~
実際に商品やサービスを開発することになった際、いま「プロダクトアウト」と「マーケットイン」のどちらの発想を採用すべきか(適しているのか)を判断する必要があります。
その判断には、商品やサービスのプロダクトライフサイクル(導入期→成長期→ 成熟期→衰退期)が大きく関係します。
プロダクトアウトの成功例である『ウォークマン』など、それまで世の中に存在していなかった商品カテゴリーの場合、プロダクトライフサイクルは「導入期」に当たります。
最初にイノベーターに注目されアーリーアダプターに普及、アーリーマジョリティに普及し“キャズム”を超えると商品はヒットします(イノベーター理論)。
そして「導入期」と「成長期」において、販売実績は右肩上がりで上昇します。
新しい商品やサービスが、それらを“欲しがる”消費者に一通り普及した後の「成熟期」になると、「マーケットイン」の発想が威力を発揮します。
主要メーカーの商品がコンビニの棚を競っていた缶コーヒーという成熟市場で、市場調査結果を分析・考察し、「朝」という“ホワイトスペース”&“ブルーオーシャン”を獲得した「WONDA モーニングショット」が、典型的な成功例です。
この「マーケットイン」発想の場合、「プロダクトアウト」発想のような画期的な商品やサービスではない既存の商品であったとしても、ポジショニングの変更によって消費者に新しいシーンやベネフィットを提供しているという革新性があることは重要です。
プロダクトアウトとマーケットインの歴史
時代によって、「いま、プロダクトアウトとマーケットインのどちらが主流なのか?」 というトレンドは変化します。
我が国で「プロダクトアウト」が主流だったのは、高度経済成長期です。「良いものを作りさえすれば必ず売れる」と言われた時代でした。
そして、バブル経済崩壊後の1990年代から2000年代に入り、一通りの商品・サービスが世の中に普及していく中、「マーケットイン」の考え方が主流となりました。
特に2000年代に入ってからは、インターネットの普及もあり、企業と消費者の情報格差が縮小(「情報の非対称性」が解消)し、企業側でも「良いものを作りさえすれば必ず売れる」という考え方から、「消費者の声を聞き、本当に必要とされる商品を売ろう」という考え方の方が主流となりました。
また、当初「マーケットイン」は製造業特有の発想でしたが、現在ではサービス業などあらゆる業界・業種で採り入れられています。
プロダクトアウトとマーケットインの融合、今後の展望
プロダクトアウトとマーケットインは、定義・特徴・メリット・デメリット等は異なりますが、優劣はなく、実務の世界でははっきりと二分されるということはありません。
前述の歴史からも分かるように、どちらか一方を選択するだけではなく、時代の流れに沿って、バランスよく融合していくことも大切です。
1970年代後半のソニー「ウォークマン」の商品企画においても、技術者発想だけでスタートしたわけではありません。創業者の井深氏の「n=1の発想」だけではなく、当時の若者たちの間に、外出先で音楽を聴きたいという潜在ニーズが見出されていたようです。
ただ、社内では「録音機能がなければ売れない」という常識が支配的で、定量調査を行うまでもなく、商品企画はうまくいかないと思われていただけです。
アップルの故 スティーブ・ジョブズ氏の、
「消費者に、何が欲しいかを聞いてそれを与えるだけではいけない。製品をデザインするのはとても難しい。多くの場合、人は形にして見せて貰うまで自分は何が欲しいのかわからないものだ」
は、一つの「真実」かもしれませんが、この言葉を多くのマーケターやリサーチャーが誤解してきました。
スティーブ・ジョブズ氏が否定したのは「顧客に欲しいものを聞く」ということです。「顧客や消費者のことをよく知ること」ではありません。実際、アップルは消費者調査を実施していないわけではありません。
商品企画のスタート段階では、企業のシーズ起点の「プロダクトアウト」だったとしても、商品企画をブラッシュアップし、マーケティング戦略や戦術を構築していく中で、「マーケットイン」発想の定量・定性の消費者調査を行うケースは、決して少なくありません。
逆に、「マーケットイン」発想で既存商品・サービスのリニューアルを行う際にも、ただ市場と消費者が求めるものだけを追求するのではなく、自社の経営資源の強みをどう活かしていくのかという「プロダクトアウト」発想が必要となることもあります。
〝失われた30年〟と言われる我が国の経済・社会において、イノベーションを起こすような目立った商品・サービスは生まれませんでした。デフレ経済期の商品・サービス開発では「いかに安くするか?」という発想が主流でしたが、2020年代に入ってから、デフレ経済の解消と賃金アップの傾向が強くなっています。
今後は低価格というユーザーニーズに寄り添うよりも、マーケットイン発想を活かしながら、プロダクトアウト発想の革新的な商品・サービスが生まれる可能性が高まること(プロダクトアウトとマーケットインの融合)が予想されます。
まとめ(プロダクトアウトとマーケットインの比較)
最後にまとめとして、プロダクトアウトとマーケットインの内容を比較してみましょう。起点の違いをはじめとして多くの相違点があります。
プロダクトアウト | マーケットイン | |
起点 | 自社(作り手)のシーズ | ユーザー(買い手)のニーズ |
姿勢 | 良い商品・サービスを作れば売れる | 求められる商品・サービスを作れば売れる |
ニーズ | 顧客が気づいていない潜在ニーズ | 顧客が「これが欲しい」という顕在ニーズ |
主なメリット | ●自社独自の技術・アイデア・製造設備などの強みを活用できる ●開発コストを抑えられる ●革新的商品やサービスを生み出す可能性がある ⇒ブルーオーシャン創出 | ●ユーザーニーズを満たした商品やサービスが提供できる ●商品やサービスを効率的に作ることができる ●需要予測が立てやすく、事業計画とマーケティング予算が組みやすい |
主なデメリット | ●商品・サービスが売れない可能性が高い⇒その場合、改善や戦略の見直しが必要
| ●「驚き」を与える革新的な商品・サービスは生まれない ●競合他社に模倣されることが多い⇒市場のレッドオーシャン化 |
影響 | 生活スタイルが変革されることもある | 生活が便利になる(生活のマイナーチェンジ) |
時代背景 | 大量生産・大量消費の経済成長期 | 商品・サービスが普及した成熟期 |
プロダクトアウトとマーケットインにまつわる、よくある質問
Q:プロダクトアウトとマーケットインのどちらが主流になるのかは、景気のように循環するのでしょうか。
必ずしも景気のように循環するとは限りませんが、マーケットインが主流となり始めた1990年代から30年も経過したため、プロダクトアウトへの注目が高まっていることは事実です。
ただし、流行のように古いものがほぼそのままの形で復活するわけではなく、マーケットイン発想により得られた経験と知見の上に、プロダクトアウト発想が活かされる、つまりプロダクトアウトとマーケットインの融合という形になっていくと思います。
Q:プロダクトアウトとマーケットインの違いは、企業の体質に左右されるものなのでしょうか。
はい、その傾向はあります。事実、70年代後半に「ウォークマン」、80年代前半にレコードに代わるCDという媒体(音楽配信の時代を先取りした音源データのデジタル化)を世に出したソニーは、プロダクトアウトの体質が企業文化に刷り込まれていると言っていいでしょう。
そして同社には高い技術力による過去の大きな成功体験のため、競合(ソニーの場合はアップル)にリードを許してしまった〝イノベーションのジレンマ〟を見ることもできます。
2001年に携帯型音楽プレーヤー「iPod」を発売したアップルは、2004年に「iPod mini」を発売しました。当時、ソニーに限らず、東芝や松下など日本の家電メーカーの携帯型音楽プレーヤーでは、高い技術力に裏付けられた多機能性が重視されていました。
それに対しアップルがとった戦略は、『ファッションアイテム』としての「iPod mini」。若い女性をメインターゲットに設定したことが奏功しました。
Q:メーカーや流通企業が消費者と一緒に商品やサービスをつくる『共創』も、マーケットインの考え方にあてはまるのでしょうか。
「コ・クリエーション(Co-Creation)」の訳語である「共創」は、たしかにマーケットインに近い発想ですが、厳密にはマーケットインに含まれる方法論というより、オープンイノベーションという独自の方法論です。
消費者だけに限らず、エンジニアがソフトウェア開発を競うハッカソンも「共創」の一つです。
Q:社内で「プロダクトアウト」と「マーケットイン」のどっちを重視するか、部署ごとに対立することはありますか。
はい、企業内でみられる、少なくはない対立の1つといえるでしょう。
同じ企業内でも、研究開発部門は「独りよがり」と言われかねない研究テーマに没頭する傾向が強かったり(プロダクトアウト重視)、逆に営業やマーケティング部門は、目の前の顧客や顧客の代弁者を自任する流通業者の意見を重視する傾向が強いでしょう(マーケットイン重視)。
よって、社内でのコンセンサスの調整は重要です。
Q:プロダクトアウトとマーケットインの融合において、最も重要なポイントを教えてください。
機械的に顧客が「これが欲しい」という顕在ニーズにこだわる=直接顧客に聞くだけでなく、「顧客や消費者のことをよく知る」ための調査(消費者調査)がポイントとなります。
マーケットインの成功事例であるアサヒ飲料の「WONDA モーニングショット」はその最たる例です。
無料ダウンロード『プロダクトアウトとマーケットイン ハンドブック』
本記事で解説した内容をまとめた資料「プロダクトアウトとマーケットイン ハンドブック(特徴・メリット・歴史・成功事例と今後の方向性)」は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。
おわりに
企業の商品・サービス開発において、プロダクトアウトかマーケットインかといった二元論に偏らず、自社がアプローチすべき市場と、磨くべき自社の強みの両者を同時に考えておくことが重要です。どのような顧客にどのようなベネフィット(便益)を、自社の何を強みとして提供するのかを明確にしましょう。
【参考ウェブサイト一覧】
・SONY ホームページ「商品のあゆみ パーソナルオーディオ」(https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/History/sonyhistory-e.html#year1979)
・アップルのプレスリリース「Newsroom」(2007年1月10日)
(https://www.apple.com/jp/newsroom/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone/)
・『オタフクソース ホームページ「お好みソースの歴史」』
(https://www.otafuku.co.jp/product/sp/okonomisauce/history/)
・ItmediaビジネスONLINE「“朝専用”で缶コーヒー戦争に革命――アサヒ飲料「WONDA モーニングショット」」笠井清志(2011年06月21日)
(https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1106/21/news003.html)
・『R25』「ジョブズの「日本をなんとかしてくれ」に応え、iPodヒットさせたマーケターの発想とは」前刀 禎明著『学び続ける知性 ワンダーラーニングでいこう』(2021年7月3日)より
(https://r25.jp/article/956428970477770625)