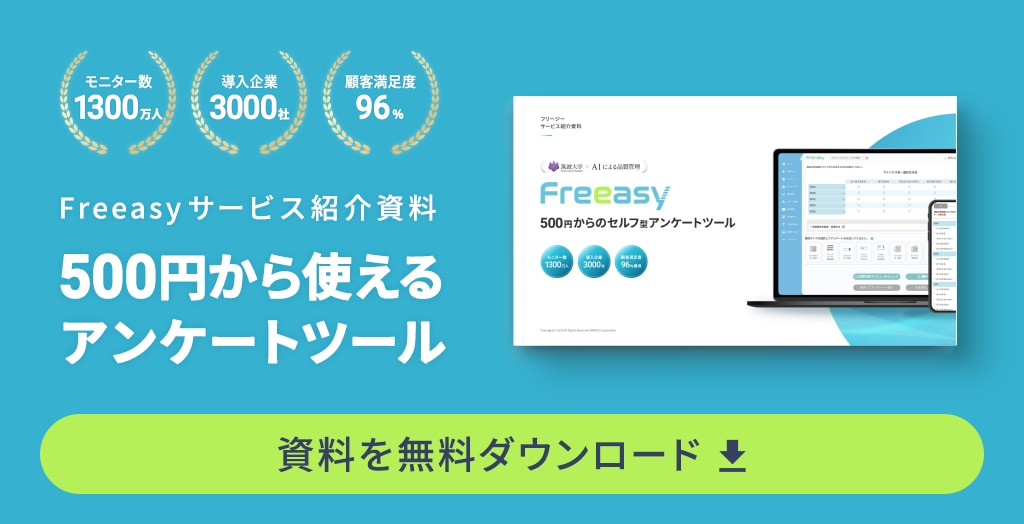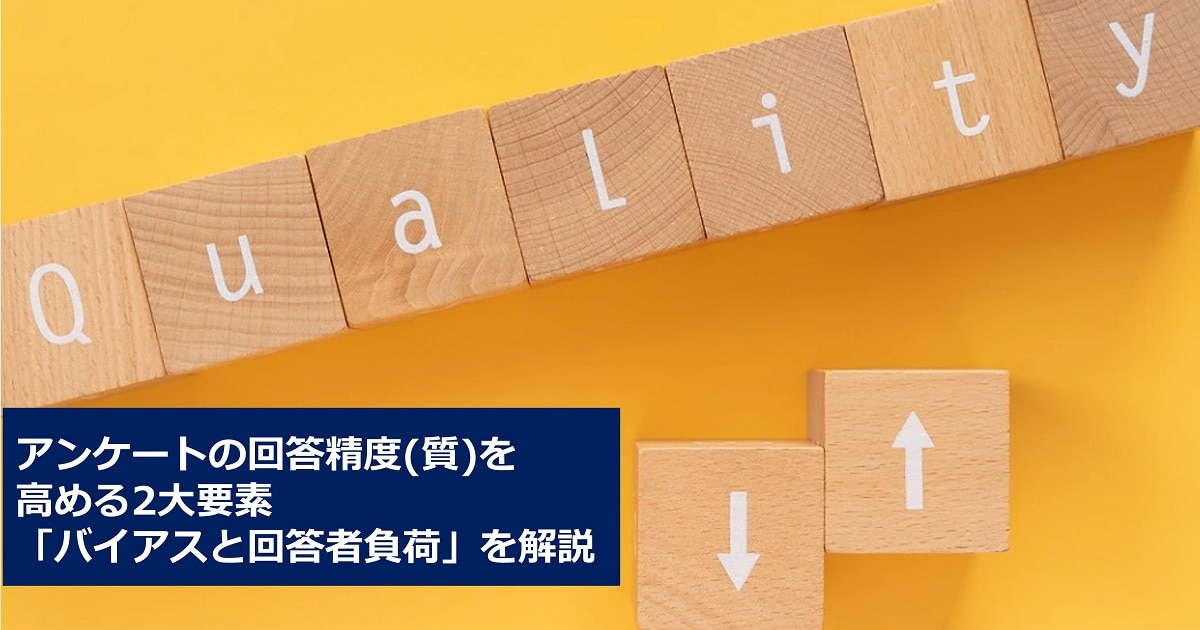
アンケートの回答精度(質)を高める2大要素「バイアスと回答者負荷」を解説
>>無料ダウンロード【お役立ち資料】調査票の作り方 基本マニュアル
目次[非表示]
- ・はじめに
- ・「高品質なアンケート結果」を入手するポイント
- ・バイアス(偏り)に注意する!
- ・①回答を誘導するような項目内容・質問内容にしない
- ・②回答者の感情を変化させるような設問にしない(プライバシーを傷つけるような質問)
- ・③本人の認識任せになってしまうような曖昧な質問内容にしない
- ・④論点が複数含まれる質問内容にしない
- ・⑤選択肢のスケールを偏らせない
- ・⑥回答者をタイトルで絞り込まない
- ・回答者負荷を考える!
- ・①質問文がわかりにくい
- ・②設問数が多い
- ・④提示する動画時間が長い
- ・⑤回答者の記憶についての質問
- ・⑥序盤から複雑な質問
- ・⑦質問のトピックが前後し答えにくい
- ・⑧選択肢のどれにもあてはまらず回答できない。
- ・無料ダウンロード『調査票の作り方 基本マニュアル』
- ・おわりに
はじめに
アンケートを実施する際、「目的」や「やり方」、「対象者」などには様々なパターンが存在していますが、どのパターンにおいても、アンケートを実施する全ての人が、“共通して求めているモノ”があります。
それは、「質の高い、きちんとしたアンケート結果を手に入れること」です。
「高品質なアンケート結果」を入手するポイント
主なポイントは、以下の3つです。
- 質の高いモニターを集める
- 質の高いアンケートを作る
- 質の高い調査会社や、アンケートツールを使う
つまり、質の高いアンケートを得るためには、まずはアンケートの実施側が「質が高いもの」を準備する必要があります。
ここでは、3つのポイントの中でも特に重要視される「質の高いアンケートを作る」ために欠かせない、「バイアス」と「回答者負荷」に焦点を当てて、詳しく解説していきます。
>>【お役立ち情報】アンケートの「基本的な作り方」を詳しく知りたい

バイアス(偏り)に注意する!
バイアスとは「回答に偏りが生じる」ことで、回答者が先入観を抱いてしまった時に生じます。
バイアスによる偏りは、アンケート自体の信憑性を下げてしまうので、アンケートの質問を作成する際は、この「バイアス」について特に注意し、常に意識しておく必要があります。
ここからは、バイアスを排除するために注意する事を、具体的な例とともにご紹介していきます。
①回答を誘導するような項目内容・質問内容にしない
例:【誘導】Q. あなたはどの位 ○○(商品)の使い心地に不満を持っていますか。
【正答】Q. あなたは ○○(商品)の使い心地についてどう感じていますか。
②回答者の感情を変化させるような設問にしない(プライバシーを傷つけるような質問)
例:夫婦関係、身体的内容、資産、信条関係 など
③本人の認識任せになってしまうような曖昧な質問内容にしない
例:【曖昧】Q.現在使用している冷蔵庫は、ご家庭にふさわしいと思いますか。
【正答】Q.現在使用している冷蔵庫のチルドコーナーの大きさは、ご家庭にふさわしいと思いますか。
④論点が複数含まれる質問内容にしない
例:【論点複数】Q.学習塾を選ぶ時、マンツーマンで講師が優れていることを重視しますか。
【正答】Q. 学習塾を選ぶ時、マンツーマンであることを重視しますか。
⑤選択肢のスケールを偏らせない
例:【選択肢の偏り】1.とても好き 2.まあ好き 3.どちらともいえない 4.とても嫌い 5.断然嫌い
【正答】1.とても好き 2.やや好き 3.どちらともいえない 4.やや嫌い 5.とても嫌い
⑥回答者をタイトルで絞り込まない
例:【タイトル】『自動車の税制変更に関するアンケート』
【正答】『自動車に関するアンケート』 ※質問の中身をある程度推測できてしまい、税制にこだわりのある自動車ユーザーだけが回答してしまう恐れがある。
回答者負荷を考える!
2つ目に大切な要素は、『回答者に正しく答えてもらえるか』という点です。
回答者への負担(回答者負荷)が大きい質問票(アンケートの質問や回答欄が記載されているフォームのこと)は、回答者が途中で離脱したり、適当に回答する恐れがあります。
回答者負荷は回答精度に影響するので、アンケートの品質確保のためには、必ず考慮しなければなりません。
回答者の負荷になってしまうこと(注意点)と、その対策について、具体的に挙げていきます。
①質問文がわかりにくい
質問文に専門用語が多用されていたり、文章が冗長だと、回答者は質問をしっかり読まずに回答してしまう恐れがあります。
【対策】下記3つのポイントを意識する。 ・専門用語を使用しない。(どうしても必要な場合は簡単な注釈を入れる) ・冗長にならない、要点のみ抑えた質問文とする。 ・「単語の名称を統一する」「語尾を統一する」など、設問間の統一感を持たせる。 |
②設問数が多い
回答しやすい質問であっても、設問数が多いと回答者が疲れ、いい加減な回答となってしまうことがあります。
【対策】設問の数は、回答にどの程度の時間がかかるかを考慮し、適切な数に設定する(15問目安)。 |
③回答の項目数が多い、マトリクスが複雑(マルチアンサー、マトリクス)
選択肢が多く、複雑だと、回答者が最後まで選択肢を読まない恐れがあります。
【対策】項目数を絞り込む(10~15項目まで)。項目が減らせない場合は、設問を分けるなどを検討する。 |
④提示する動画時間が長い
最後まで閲覧されず、適切な回答を得られない恐れがあります。
【対策】提示する動画時間を短くする(15秒、30秒程度)。 |
⑤回答者の記憶についての質問
「1ヶ月前に試食したデザートの評価」など、回答者の記憶を頼る設問は負荷が高くなります。詳細まで思い出せず、適切な回答を得られない恐れがあります。
【対策】できる限り、その場でサービスを提供し回答してもらう。難しい場合は、お店の外観画像を提供したり、アンケート構成を通じて、少しでも記憶を呼び起こしてもらい、回答をしてもらう。 |
⑥序盤から複雑な質問
アンケートの序盤に複雑で回答しづらい設問が設定されていると、回答者が抵抗を感じ、離脱やそこから先に進まない可能性があります。
【対策】序盤は回答しやすい質問とする。 |
⑦質問のトピックが前後し答えにくい
例えば、次のような構成にしてしまうと、Q1とQ2の内容が繋がっておらず、回答者負荷が高まります。
Q1. 所有している自動車をお答えください。
Q2. 月々の生活費はいくらですか。
Q3.所有している自動車は主に何に使いますか。
【対策】関連する質問はグルーピングし、回答しやすい並び順にする。大項目・中項目・小項目を正しく使い分けて、テーマごとに設問が続く形を心がける。グループが分かりやすいよう見出しをつけるのも有効です。 |
⑧選択肢のどれにもあてはまらず回答できない。
例えば、次のような質問だと、4つの選択肢に該当しない趣味を持った回答者は強制的にどれかを選ばざるを得なくなります。
Q. どのような趣味をお持ちですか。
1.ショッピング 2.登山 3.ツーリング 4.読書
【対策】該当しない場合を想定し、「この中にはない」「あてはまらない」「その他」等の選択肢を設けておくと、回答者の負荷を軽減することができます。 <正答>Q. どのような趣味をお持ちですか。 |
>>【お役立ち情報】早速アンケートを簡単に作りたい!「アンケートツール」について詳しく見る
無料ダウンロード『調査票の作り方 基本マニュアル』
下記資料は本記事に関連した「調査票の作り方 基本マニュアル」です。無料でダウンロードできますので是非ご活用ください。
おわりに
せっかく時間もお金もかけてアンケートを実施するなら、ここで述べたポイントをすべて取り入れて、自信をもって「質が高い!」と言えるアンケート結果を集めてください